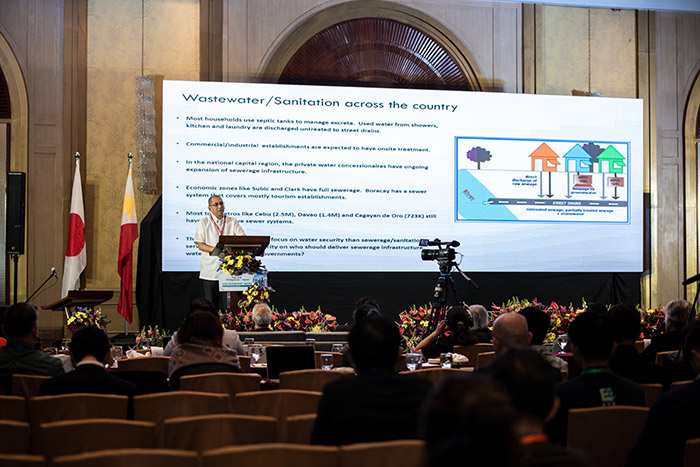第2回日本・フィリピン環境ウィークを開催。
3日間で総勢1000名超が参加 !
ダイジェスト動画
第2回日本・フィリピン環境ウィークを開催。
3日間で総勢1000名超が参加!
環境ウィークは、日本とパートナー国の環境担当省庁が連携し、ハイレベルの政策対話、展示会、ビジネスマッチング、セミナーなどを一体的に開催するイベントです。環境インフラのトップセールスを行うとともに、両国における環境ビジネスの機会を効率的かつ効果的に創出することを目的としています。
2017年以来、アジア各国で開催されており、2025年1月13日~15日には、フィリピン共和国環境天然資源省との共催で、第2回日本・フィリピン環境ウィークがマニラで開催されました。
日本・フィリピン両政府をはじめ、地方自治体、民間企業、研究機関、国際・地域機関、NGOなど多様なステークホルダーが参加し、両国の環境課題への理解を深めるとともに、グリーンビジネスの成長に向けた協力の可能性を探りました。
この記事のコンテンツ
民間企業がビジネスピッチで自社の魅力をアピール!
省エネ、廃棄物処理、大気・水質汚染、フードロス、防災などの分野で活躍する日本とフィリピンの環境ビジネス企業が、自社の脱炭素技術によって強靭な社会の構築にどれだけ貢献できるかを力強くアピールしました。
基調講演:
竹本和彦氏(国際応用システム分析研究所議長・OECC理事長)は、本イベントが多様なステークホルダーの協力の場であり、脱炭素化と持続可能な社会のためには総合的アプローチが不可欠だと強調しました。
渡辺陽子氏(アジア開発銀行環境課長)は、気候変動対策としてフィリピンのパートナーシップ戦略や、生物多様性管理、汚染対策、循環型経済の取り組みを紹介しました。
パネルディスカッション:
5名のパネリストが地方自治体、学界、プライベートセクターの立場から、それぞれの取り組みを紹介しました。その後、フィリピンが直面する環境課題の解決に向けて、日本との協力のあり方や、その効果的な促進策について議論が交わされました。さらに、次のテーマへとつながる多様な課題が提示され、今後の展望についての提案が共有されました。
PLENARY SESSION
Collaboration Opportunities toward Climate-Resilient and Sustainable Philippines
Moderator

Ma. Teresa Lopez Pacis
Assistant Vice President for Corporate Affairs Apex Mining Co, Inc,

Rosemarie U. Chavez
Assistant Department Head II of General Services, Mandaue City

Dr. Patricia Ann J. Sanchez
Professor of School of Environmental Service and Management Unv. of Philippines

TAKAHASHI Gen
GM of Public Sector Partnership Global Administration Department JFE Engineering Corp.

Dr. TAKEMOTO Kazuhiko
President OECC Chair, IIASA

Arnold Grant S. Belver (EnP)
Development Management Officer IV, Policy Research and Development Division CCC
環境金融や気候変動など8つのテーマ別セミナーを官民連携で開催
政府や民間セクターとの交流機会の提供、技術協力の促進、持続可能な開発に向けた両国の情報共有が行われ、日本とフィリピンの環境分野における協力関係がさらに強化されました。
参加者からは、両国の環境課題に対する具体的な取り組みやニーズを学ぶ貴重な機会であったとの声が多く聞かれました。
発表資料のダウンロードはこちらから本セッションでは、規制当局、金融機関、企業、国際機関などの関係者が集まり、環境金融に関する最新の取り組みや動向について意見を交わしました。
政府機関からはフィリピン証券取引委員会(SEC)が登壇し、金融セクターでは世界銀行、アジア開発銀行(ADB)、BPI(バンク・オブ・ザ・フィリピン・アイランズ)、三井住友銀行(SMBC)が参加しました。また、民間企業としてAyalaグループのACENやアスエネも議論に加わり、日本とフィリピン双方の環境ビジネスの発展に向けた意見交換を行いました。
特に、民間企業が事業活動と金融支援をどのように結び付け、ネットゼロ排出社会への移行を促進するかを議論しました。また、ASEANにおける統一的な炭素価格メカニズムの観点から、環境情報開示や金融の現状を分析し、民間の金融資源と企業のニーズをどのように調整すれば、すべての資金の流れをパリ協定の目標に適合させられるのかを検討しました。
ASEAN地域では約6億8千万人が暮らし、経済成長が著しい一方で、産業排水や生活排水処理施設の整備が十分に追いついていない現状があります。フィリピンも例外ではなく、水環境ビジネスの発展と水環境改善に向けた取り組みが急務となっています。本セッションでは、日本とフィリピンの間でビジネス機会を創出することを目的に、多くの技術を紹介しました。
フィリピンの現状については、生活排水の腐敗槽からの汚水浸透が主要な課題として挙がり、下水システムの導入が必要であることを強調しました。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)モデルへの適用可能性など、新しいアプローチについても紹介しました。
一方、日本政府は、浄化槽システムや水の再利用技術を紹介しました。さらに、7社の企業が自社の技術を発表し、今後の水環境改善に関連するビジネス機会について情報を共有しました。
本セッションでは、気候変動緩和に向けた取り組みや課題を紹介し、フィリピンにおけるネットゼロ・脱炭素社会の実現に向けて、日本とフィリピンの民間セクター間の協力の可能性を探りました。環境省、フィリピン環境天然資源省(DENR)、フィリピン証券取引委員会(SEC)がそれぞれの取り組みを発表しました。
特にSECは、企業の情報開示を促進するためのインセンティブ制度を紹介し、この制度により高いコンプライアンス率が達成されていることを報告しました。しかし、データの信頼性や技術の発展が今後の課題として挙げられました。
DENRは、今後の協力機会として、二国間クレジット制度(JCM)を活用した技術移転や民間セクターへの投資促進、MRV(測定・報告・検証)システムの強化、そして林業を活用したカーボン市場のパイロットプロジェクト創出を提案しました。
後半では、JCMを含む具体的な協力の枠組みやフィリピンでの実績について説明があり、JCMを活用した新たなコラボレーションの機会について各企業から発表が行われました。
本セッションでは、フィリピンにおける持続可能な電気・電子機器廃棄物(E-waste)管理とリサイクルの促進に向けた取り組みについて議論しました。フィリピン環境天然資源省(DENR)と日本国環境省は、両者の環境協力覚書やE-waste及び重要鉱物に関する日ASEAN資源循環パートナーシップ(ARCPEC)に基づき、協力を進めています。
フィリピンにおけるE-wasteリサイクルの現状と課題、EPRや有害廃棄物管理に係る法制度の動向、E-wasteの適正な回収と環境上適正なリサイクルの推進に向けた方策、日比両国における潜在的なビジネス機会等について意見交換が行われました。E-waste管理における責任分担、資金メカニズムとインセンティブ、地方自治体の参画強化、官民の能力向上、優れた技術の導入、消費者の意識改革等が重要なポイントとして示されました。
本セッションでは、フィリピンにおける循環型経済と廃棄物管理の取り組みや課題を紹介し、日本とフィリピンの民間セクター間でのさらなる協力の可能性を探りました。
フィリピン側の登壇者は、循環型経済と強固な廃棄物管理システムを促進するためには、両国政府が相互に支援する政策や規制を確立することが不可欠だと述べ、特に廃棄物からのエネルギー(WtE)ソリューションの導入によるインセンティブ提供が重要であるとの意見を示しました。また、WtEに特化した日本企業とフィリピンの地元産業が協力し、研究や技術革新を通じて持続可能な技術への投資を進めること、さらに国際的な連携を強化しながら各国の能力強化を進めることが必要であるとの指摘がありました。加えて、消費者の行動変革が不可欠であることも議論されました。
7つの企業が循環型経済や廃棄物管理に関連する事業を紹介し、活発な意見交換が行われました。
本セッションでは、フィリピンおよび東南アジア諸国で検討されている気候変動適応対策の最新技術や動向について情報共有が行われました。
日本による官民連携(PPP)を活用したEWSの展開が紹介されたほか、ケソン市からはフィリピンの全市町村において策定が求められている「強化版地域気候変動行動計画」(LC-CAP)への対応、循環型経済、水・食料確保に向けた取り組みが発表されました。
フィリピン企業からは、気候変動と環境の課題に対応し、水資源をより効率的に管理することを進めていることや、洪水被害軽減への努力、廃棄物削減の取組が共有されました。
気候適応対策において注目を集めている自然を活用した解決策(NbS:Nature-based Solutions)についても多く議論が交わされ、世界銀行フィリピンオフィスから世界各地での成功事例についても共有がなされました。インドネシアの企業からは、パームシュガー事業が気候適応策だけでなく、生物多様性対策としても有効であり、社会的・環境的な持続可能性にも貢献できることが示唆されました。
CEFIA(クリーンエネルギー・未来イニシアティブ・アジア)は、ASEAN地域におけるクリーンエネルギーの普及と脱炭素技術の開発を加速するため、官民協力を促進するプラットフォームとして設立されたイニシアティブです。
本セッションでは、日本の経済産業省と連携し、フィリピンにおけるマイクログリッド技術の活用可能性について議論が行われました。マイクログリッドは、風力発電や太陽光発電と蓄電池を組み合わせた再生可能エネルギーの統合システムであり、CEFIAのフラグシッププロジェクトとして位置づけられています。
このプロジェクトに参加している日本の企業は、フィリピンでのマイクログリッドシステムの展開を進めており、フィリピンにおけるマイクログリッドの有用性を発表しました。
さらに、その他の日本企業も日本の支援プログラムを活用し、ASEAN・アジア地域で進めているさまざまなパイロットプロジェクトの事例を紹介し、今後のフィリピンとの協力の可能性について発表しました。
参加企業や来場者からの声
-
情報交換や自社広報の貴重な機会
イベントは、情報交換や自社広報の絶好の機会となりました。 -
無料での出展とフィリピンでの関係構築
事前登録が必須であったが、出展が無料で、フィリピンにおける官民双方との関係構築やPR活動ができました。 -
ビジネスピッチや展示・商談ブースの効果
ビジネスピッチや展示・商談ブースの実施は非常に効果的で、実際のビジネスに活用できる機会となりました。 -
フィリピンの環境技術水準やニーズの理解
フィリピンにおける環境分野の技術水準やニーズを把握することで、今後のビジネス展開において重要な知見を得ることができ、長期的なビジネスチャンスにつながる可能性を感じました。 -
幅広いセミナーテーマ設定
官民連携によるソリューション、地域社会の関与強化、成功事例の紹介などの発表を増やしてほしい。 -
政府・民間双方の参加と今後の協力の可能性
政府・民間双方が参加し、現在の協力関係および潜在的な連携の可能性が示され、両国のハイレベルが一堂に会したことが非常に評価できる。
関連情報:
フィリピン商工会議所とJPRSI事務局を務める(OECC)が連携の覚書を締結しました。
関連記事をご覧ください。