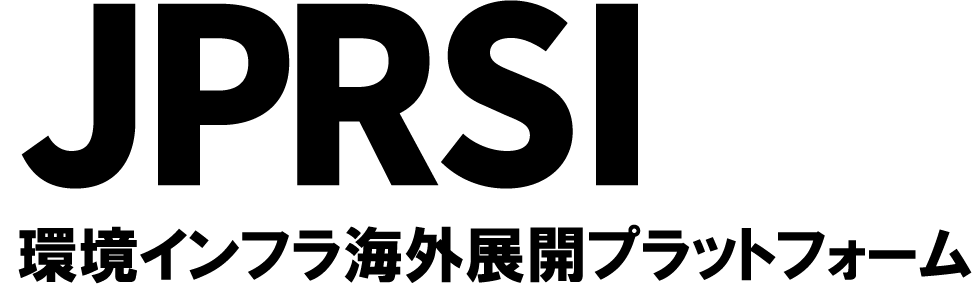現地の声:日本の技術によるソリューション事例
2025.7
ベトナム:廃棄物発電事業
- 事業計画作成からファイナンス、建設、運転までをトータルプロデュース -
JFEエンジニアリング株式会社 ⅰⅱ

JFE エンジニアリング株式会社は、現地ベトナムのトゥアンタインエンバイロメント社(以下、トゥアンタイン社)と共同で、T&Jグリーンエナジー社を設立し、ベトナム国バクニン省で廃棄物発電プラントを建設し発電事業を開始しました。また、2024年1月にはプラントの竣工式も行われ、ダン・クオック・カイン天然資源環境相、八木哲也環境副大臣をはじめ、ベトナムと日本の政府、企業関係者が参加をしました。
このような大規模な事業を海外で展開するまでの経緯など、事業実施に至るまでのストーリーとその裏に隠された苦労や企業・ご担当者様の努力も含めて、事業発足当時、ベトナム現地法人の社長を務めていらっしゃったJEFエンジニアリングの大原隆信様にお話をお伺いしました。
事業化の背景・経緯
JPRSI 事務局(以下、事務局): 本日はお時間ありがとうございます。早速ですが、本事業の発足の経緯として、事業化に至る背景からお話をお伺いできますか。
JFE エンジニアリング大原様(以下、JFE大原、敬称略): 私は2012年4月にベトナムに赴任しました。ベトナムに限らず、東南アジア全般に言えることだと思いますが、これらの国々では、廃棄物処理の前に、上下水処理の問題が顕在化します。そのため、当社としては、当時はJICA円借款による下水処理場建設案件の受注を目指し、ベトナムに駐在事務所(のちの現地法人)を構えました。なんとか、2015年にハノイ近郊の国家イノベーション拠点とされているホアラックハイテクパーク内の3万6000m3/日の下水処理場建設案件を受注し、その後、2018年にハノイ市最大規模のエンサ下水処理場(27万m3/日)の建設工事を受注することができました。エンサ下水処理場は、人口90万人程度を対象にした大型下水処理場で、当社の海外案件としては最大規模の案件になります。
この間、ノイバイ国際空港のジェット燃料の給油設備や、民間企業様の工場建設も受注することができ、当社としてベトナムでの建設工事のノウハウを蓄積することができました。
このように円借款案件を2件受注できたのですが、このころベトナムの公的債務比率削減の動きが加速し、ベトナムがODAを使ったインフラ整備から民間資金活用によるインフラ整備に舵を切り、円借款による将来の下水処理場案件の見通しが全く立たなくなってきました。そのため、2017年ごろからODA案件の受注を主軸にした事業方針を考え直す状況になっていきました。
そこで、当社のパーパスである「創る、担う、つなぐJust For the Earth」を軸に、「人々の生活の基盤を支える」という理念のもと、ベトナムにおける事業については自らが出資して事業化をしていくという方向に舵を切りました。
事業方針変更後、廃棄物、上下水、再エネを切り口に事業化の機会を模索する時期が続きましたが、上下水は、管渠への投資が巨額となることや、土地収用の手続きが煩雑で長期化しそうなことから、再エネはバイオマス燃料調達の困難さから、それぞれなかなか糸口がつかめず、どちらかというと、廃棄物の方に事業化の糸口を見出すことになりました。
糸口を見出すにあたっては、ベトナムで廃棄物処理の事業開発をするには、「現地事情に通じたローカルパートナーがいないと、廃棄物の収集や許認可の取得もままならない」と考え、まず、「旧態依然としたベトナムの廃棄物処理事情を変えるぞ!」という気概を持った現地企業を探すことにしました。
ひとくちにローカルパートナーを探すといっても、ベトナムだと国営(民営化されたところも含め)か、民間か、という選択肢があります。国営企業とは話をする機会は多々あったのですが、積極的に一緒に事業を作っていくという動き方がなかなかできず、先に進むことができませんでした。これは企業文化の違いだと思います。
そこで、ベトナムの民間廃棄物処理会社を徹底的にリストアップし、片っ端からベトナム人スタッフにコンタクトしてもらい、外資との協業に関心がある企業を探し出そうとしました。しかし、廃棄物の適正処理という考え方自体が根付いておらず、外資と一緒に事業をすることに関心を持つ企業はほとんどいないことに気づかされました。現場を見せることにも良い反応はなかったため、まず、顔を合わせて面談する、という最初のステップを踏むことすら困難な状況でした。
やる気のある民間企業とスピード感をもって事業を進めたいと努力はしていましたが思うようには見つからず、必死になって探していたところ、2018年にハノイで開催された環境ウィークで今のパートナーであるトゥアンタイン社とつながり、本件の事業化に向けた糸口を見つけることができました。
糸口が見つかったのは、当社が廃棄物発電プラントの建設業者と、廃棄物処理事業者という2つの顔を有しているというユニークな企業であることを、トゥアンタイン社が評価してくれたことにあります。当社はプラント会社としては珍しく「J&T環境」という廃棄物処理を行う事業会社をグループ会社として有しています。
本件を進めるにあたっては、トゥアンタイン社に日本に来てもらい、当社の自治体様向けに納入した清掃工場に加え、J&T環境が保有する廃棄物処理工場の操業状況も見てもらい、当社が建設だけではなく、その後のO&Mのノウハウ、とりわけ、本件の肝でもある、産業廃棄物の取り扱いにも知見があることを理解してもらえたことが、合弁事業立ち上げに向けて進む糸口になったのです。
事務局 : バクニン省で事業を行っていらっしゃいますが、自治体の廃棄物処理計画等とのつながりはどのようになっていますか。
JFE 大原 : ベトナムはマスタープランに則って廃棄物処理の場所や方法等が決まっていますので、対象となる廃棄物やそれを処理する地区などについては計画と合致している必要があります。まず、このマスタープランに則るということが大事です。
事務局 : 事業採算の構図について伺えますか。
JFE 大原 : 廃棄物発電事業の収入源は廃棄物処理費と売電収入の2つのみです。
売電に関しては、ベトナムのFIT制度を活用しています。廃棄物処理費に関しては、自治体からの一般廃棄物処理から得られる処理費に加え、トゥアンタイン社が周辺の工場から集める産業廃棄物の処理費があります。自治体からは350t/日、工場からは150t/日を集める計画です。
ベトナムにおいては一般廃棄物の処理費はかなり低く、残念ながら一般廃棄物のみですと当社の事業化採算ラインには乗ってきません。
現地パートナーとの関係構築
事務局 : 本案件にはどのような関係者が関わっていますか。
JFE 大原 : 合弁会社であるT&Jグリーンエナジーへ出資しているのは、当社とパートナーのトゥアンタイン社の2社です。また、J&T環境からは工場長を派遣してもらい、操業や人材育成を支援してもらっています。その他、当社が出資するまでの間、環境省からは強力なバックアップをいただきました。
事務局 : 現地パートナーのトゥアンタイン社との関係構築について教えてください。
JFE 大原 : 先ほど触れた通り、2018年の環境ウィークがトゥアンタイン社とタッグを組むきっかけになりました。
同社は、この業界の大部分の会社とは異なり、海外の企業と組んででもベトナムの廃棄物処理システムを変えたいという意気込みの強い、前向きなマインドを有する企業だったため、関係構築がスムーズにできたのだと思います。
一方で、お互いを理解するための歩み寄りも必要だったことは事実です。トゥアンタイン社は、現会長がバイクの部品回収から大きく成長させた会社で、会長の一声で物事が決まります。一方、大部分の日本企業がそうだと思いますが、当社の場合は、決定を下すまでには、物事によってはホールディング会社の審議まで持ち込む必要があります。いわゆるオーナー企業であるトゥアンタイン社とは、決裁を下すまでの時間やリスクの捉え方は大きく異なるので、この点での調整には苦労をしました。
苦労の連続
事務局 : 海外への事業展開にはご苦労が多いことと思いますが、今回の事業発足やそれ以外でも特に困難な点やそれを克服した エピソードなどがあればお聞かせください。
JFE 大原 : ベトナムの役所の手続きが複雑で、ローカルパートナーがいても承認プロセスの把握自体に苦労しました。本事業が廃棄物発電事業の先駆けとなる事業ということもあり、自治体側も経験がなく承認までにどのくらい時間がかかるのか等、時間軸の調整は非常に大変でした。さらに、バクニン省からどの程度の廃棄物が収集できるのか、産業廃棄物がどの程度収集できるのかを、社内や金融機関などに納得してもらう資料を作成することに苦労しました。
事務局 : 資金調達の面で苦労した点などはありますか。
JFE 大原 : 廃棄物処理契約、PPA等、ベトナムでは、まだまだプロジェクトファイナンスが成り立つようなレベルには至っていません。我々が本案件を組成したころは、銀行からの融資には目途が立たず、自社で用立てするしかないのか…、といった話まで出たほどでした。いろいろな金融機関の方と交渉していく流れで、国際金融公社(IFC)にフィンランドの気候ファンドを紹介していただき、ここがトゥアンタイン社のリスクを取ることで、当社およびトゥアンタイン社の保証で融資をアレンジすることが出来ました。
IFCにしたことで、第三者機関を雇って環境社会影響評価(ESIA)や、モニタリングの仕組みを構築する必要が出てきたため、現在も、現地小学校で出前授業をしたり、近辺の村を回って、本プロジェクトの影響がないかなどの意見を収集したりしています。本案件のファイナンス情報はIFCのサイトでも公開されていますので、ご参考にしていただければと思います。
事務局 : ODA事業と比べて難しい点などはありますか。
JFE 大原 : もともと我々がターゲットとしていた円借款の建設請負工事は、建設を行い、性能要件を満たしたら設備を引き渡して終了という形がほとんどですが、本件は投資事業ですので今まさにスタートラインに立ったばかりです。これから事業運営をし、利益を出していかなければいけないという状況のため、事業として成功するかどうかも含めて、これからが勝負です。ここはODA事業とは全く違う困難さがあります。
 |
|---|
ベトナム バクニン省廃棄物発電施設 起工式 |
これから
JFE 大原 : 今後の発展・展開などを教えてください。
事務局 : さきほども触れた通り、これからが正念場であり、ようやくスタート地点に立ったというのが現状です。今後の発展・展開としては、この事業をひな型として、適切な契約形態、プラントのスペック、プラント運用方法等を磨き上げ、東南アジアで類似案件をどんどん作っていきたいという思いがあります。
 |
|---|
ベトナム バクニン省廃棄物発電施設 竣工式 |
先ほど申し上げたように、当社のパーパスは、生活の基盤を「創る、担う、つなぐ」ことにあります。このような投資案件を増やすことによって、「創る」だけではなく、プラントの運営を通して、東南アジアの人々の生活を支えるインフラを「担う」という部分を強化していきたいと考えています。
当社横浜本社内にあるグローバルリモートセンターでは、国内外のプラントをつなぎ、遠隔で様々なプラントの情報を解析し、より効率的な運営ができるように支援をする「つなぐ」にあたる活動も行っています。また、「つなぐ」という視点では、プラントのある地域の皆様とのつながりをしっかりとしたものにし、当社のプラントが地域に必要とされるインフラであることを理解してもらい、支えていただくことが大事だと考えています。
将来的には、そうした地域のつながりが、別な地域、国の方につながり、「我々のごみを何とかして欲しい」と声をかけていただけるようになることが理想です。
 |
|---|
|
担当者様紹介 JFEエンジニアリング株式会社 日本鋼管(現JFEエンジニアリング)入社後、農業系スタートアップ企業等を経て、2012年から駐在員 事務所所長、現地法人社長として、ベトナム市場開拓に従事。2023年4月より環境本部リサイクルビジネス推進事業部担当部長。 |
|---|
- 本資料はJPRSIが信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性・確実性を保証するものではありません。
- 本資料に従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するもので、JPRSIは何らの責任を負うものではありません。
- 本資料へのリンクは自由です。それ以外の方法で本資料の一部または全部を引用する場合は、出典として「JPRSI(環境インフラ海外展開プラットフォーム)ウェブサイト」と明示してください。
ⅰ 記事本文は、JPRSI海外展開事例紹介として、2024年4月にJPRSI事務局がまとめた「JPRSI海外展開事例紹介Vol.1」の再掲です。内容は掲載当時のものです。
ⅱ 冒頭写真:ベトナム バクニン省廃棄物発電施設完成全景
【参考】
ベトナム国で大型廃棄物発電事業に参画~事業計画から建設・運転までトータルプロデュース~
https://www.jfe-eng.co.jp/news/2021/20211216.html
バクニン省における廃棄物発電 (JCM事業)
https://gec.jp/jcm/jp/projects/21pro_vnm_01/
廃棄物発電プラント・プロジェクトを通じ、ベトナムの低炭素経済の移行を支援(2021年11月2日)
https://www.ifc.org/ja/insights-reports/2021/cs-tandjgreen-energy-company-vn-2021