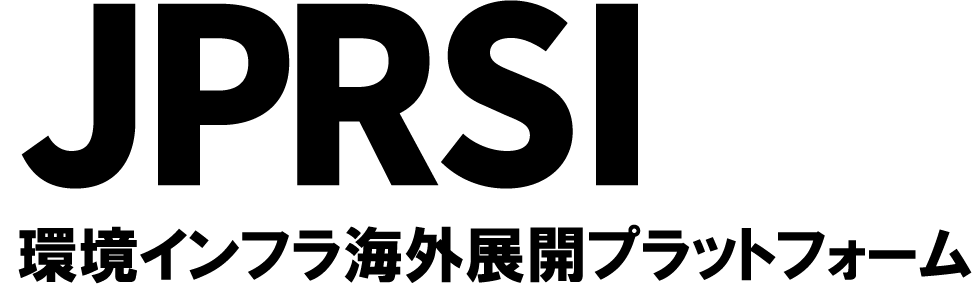現地の声:お伝えしたいこんな魅力
2025.10
パキスタン
―30歳以下人口1.6億人!i 省エネルギーにも大きなチャンス―ii

パキスタン・イスラム共和国の概要
パキスタンと聞いて皆さまはどのようなイメージを頭に思い浮かべるでしょうか? 日本では「テロが多発する国」というイメージが先行しているかもしれません。少し上の世代であれば1970年代、米中国交正常化の交渉過程でパキスタンが大きな役割を果たしたiiiことや、アントニオ猪木とパキスタンの英雄アクラム・ペールワンの伝説の対戦iv等も思い浮かぶかもしれませんね。国際的な経済活動に関心が強い方であれば、中国が推し進める一帯一路(One Belt One Road)政策においてきわめて重要な役割を占める国であることも認知されているでしょう。
結論から言えば、パキスタンはグローバル企業に非常に注目されている市場の一つです。vその理由は、1)3億人に近づく巨大な人口(2023年国勢調査で2.4億人)、2)人口の35%が15歳以下、66%が30歳以下viという若年層の多さ、そして3)アジアと中東の結節点にあるという地政学的重要さ、の3つです。1)、2)双方の背景から、労働年齢人口が増加し続ける「人口ボーナス」期が当面長く続くことは間違いありません。地理的にも、アジアの一部でありながらすぐ「対岸」が中東という立地から、中東マーケットへの輸出拠点としても機能しています。またこの数十年、日本からはインドへの進出・事業展開が目立ってきましたが、直近で米・印関係に隙間風が吹く一方で米・パ関係が改善していることから、これまで以上に新興市場として注目が集まっているのです。
具体的には消費財分野ではネスレ、ユニリーバ、P&G、飲料分野ではコカ・コーラ、ペプシコ、エネルギー分野ではシェル等がパキスタン市場で高い利益率を上げています。日本企業でもトヨタや三菱電機は現地パートナーとも連携しつつ、しっかりと根を下ろしています。現地報道によればグローバル企業は近年、パキスタンでのビジネスで大きな利益を上げており、外貨送金の制約が解除されたこともあって、本国に投資額を上回る金額を還流していることが統計的に示されています。vii
また下の写真のように、街中で見かける自動車の90%以上が日本車である等、「親日度」が極めて高い国です。日本の戦争に至る経緯や戦後復興の歴史が英植民地から独立したパキスタン国民感情と共鳴した面もあり、現地では日本に対する敬意が根強く存在します。筆者の現地駐在経験からも親日度の高さは間違いなく、この点も日本企業には追い風と言えるかもしれません。
 |
|---|
街中ですれ違う車両は大部分が日本車。 |
省エネ需要の取組が進む
パキスタンが魅力的市場であることは間違いありません。しかし、既にグローバル企業が開拓済みの市場で日本企業が互角に戦うことは難しいでしょう。そこでご紹介したいのは、これからパキスタンで実需が拡大することが確実視されるものの、まだ明確に市場が成立しきっていない省エネに関する製品・サービスです。パキスタンは国家戦略としてエネルギー効率化に舵を切っており、2030年までに温室効果ガス排出量を最大20%削減すると国際的に約束しています。そして、達成に向けたロードマップの中で産業・住宅・輸送・電力・農業の5分野を優先領域と位置づけて、各分野で取組を本格化させました。
パキスタンにおけるエネルギー消費において、特に家庭部門では冷房・冷蔵機器の電力消費が突出しており、効率化のインパクトは甚大です。高温多湿な気候のもと、エアコンと冷蔵庫は生活必需品でありながら、電力網への負荷が大きい状態が続いていました。長年パキスタンは電力不足に苦しんでいましたが、世界銀行や日本政府を含む二国間ドナー(援助)viiiは発電能力の増強と送配電ロスの削減、そして電力料金改定を伴う電力セクター改革といった“上流”を優先してきました。このため電力を消費する商品、特に省エネ製品の普及や開発促進の取組は“マイナー”なものでした。しかし、2015年頃から「電力の有効活用」、すなわち省エネに関連した取組の重要性が認知され、電力不足という国家課題の解決と未来志向の温室効果ガス削減の両立を達成できる取組が国家戦略の一部に位置づけられたのです。
省エネを「見える化」
その一翼を担ったのが、国際協力機構(JICA)による技術協力プロジェクト「パキスタン国 省エネルギー基準及びラベリング制度にかかる戦略策定・推進プロジェクト」です。JICAも他ドナー同様、2015年以前は特に太陽光発電による発電量の確保や送配電ロスの削減、それに貢献する人材育成を中心に電力セクターの支援を行っていました。ただ「日本の強みをより生かせる支援を」という発想で2015年以降NEECA(パキスタン省エネルギー庁)と連携し、製品の省エネ性能を評価・表示する制度の構築を支援。IEC規格に基づく試験方法の研修や、製品の買上試験による性能確認等、制度の実効性を高める取組が完了しました。
このプロジェクトでは、家庭用エアコン(AC)と冷蔵庫を対象に、「省エネ基準(MEPS)とラベリング制度(ES&L)」の導入を支援し、製品のエネルギー効率を「見える化」することで、消費者の選択を促し、非効率な製品を市場から段階的に排除することを目指しています。日本の家電量販店では当たり前になっている省エネ性能表示が、製品ごとに可視化されることを目指し、政府内ではJICAが策定した省エネ基準の承認プロセスが現在進んでいると聞いています。
この取組は単なる技術支援にとどまらず、日本企業にとって、パキスタン市場開拓の“礎”となる可能性を秘めています。日本の家電メーカーは、長年にわたり高効率・高品質な製品開発に注力してきました。インバーター技術や断熱構造、スマート制御等、世界トップクラスの省エネ技術を有していることは言うまでもありません。ラベリング制度が整備されれば、こうした技術力が数値として可視化され、消費者は「どの製品が電気代を抑えられるか」を一目で判断できるようになります。これまで現地で優先されてきた価格競争だけでなく性能競争も始まれば、日本企業の省エネ製品がこの巨大市場に食い込めるようになることでしょう。
JICAのプロジェクトは、NEECAの制度設計だけでなく、試験機関の能力強化やメーカーとの対話の場づくりにも取り組んでいます。こうした「制度の根っこ」に日本が関与していることは、企業にとっても大きなアドバンテージと言えるのではないでしょうか。そして、将来的には冷蔵庫・AC以外の製品にもラベリング制度が拡張される見通しであることも触れておかなければなりません。照明・洗濯機・テレビ等、日本企業が得意とする分野が次々と対象になることまで視野に入れれば、今がまさにパキスタン市場の調査を開始するタイミングと言えるでしょう。
このほか、再生可能エネルギーも日本製品の展開チャンスがあると言えます。特に太陽光発電関連機器は中国から低価格な商品(一部は粗悪品とも言われる)が大量に流入しているだけに、質が高く、長持ちする日本製品がひとたび口コミで人気を呼べば普及の糸口が見えてきます。2011年にJICAが無償資金協力で、パキスタン政府の計画省や土木委員会本部(PEC)内に発電量測定パネルを設置した経緯もあり、一部の政府関係者は日本製太陽光発電製品の信頼性の高さを認識しています。
パキスタン市場攻略のヒント
パキスタンが魅力的な市場であることも、日本企業が得意とする省エネ技術の将来性もわかったけど、リスクが大きいのではないか?、という声もあるかもしれません。
テロの危険性が高いのではないか?、いえ、パキスタンにおけるテロはアフガニスタンやイランとの国境付近、外国人がほとんど訪問しない西側に集中しており、首都イスラマバードや東部ラホール等主要なビジネス中心地ではそれほど危険はありません。
日本企業がビジネスを行う際、現地で協力してくれるパートナー企業、雇用可能な現地従業員が確保できないのではないか?、いえ、JICAが世界各地で実施する「全世界ICT産業連携振興プロジェクト」の一環として公開している「High Tech Pakistan」のウェブページixを見るとパキスタン企業と日本企業の協業事例や日本企業向けにパキスタン人従業員候補を育成する企業(Japan Station)が紹介されています。パキスタンには欧米で教育を受けた若者も多く存在しており、しっかりと採用活動を行えば優秀な人材の確保は可能です。
他方、筆者から見てリスクがあることを指摘せざるを得ないのは、パキスタン特有の行政・承認プロセスの遅さと為替リスクの高さです。実感として、パキスタンは生活するには大変暮らしやすい国ですし、インドに比べれば各種交渉もそこまでハードではありません。しかしながら、いざ仕事となるとパキスタン政府の手続きの遅さ、正式承認までのハードルの高さにはたいへん苦労しました。現地でのビジネスを円滑に進めるためには既にパキスタンで事業をしていて、政府関係者とも親しい信頼できる人物、現地パートナーの発掘は一つのキーポイントでしょう。
加えて、パキスタンの通貨(ルピー)が不安定であることへのリスクヘッジは不可欠です。パキスタンは長年財政赤字に苦しんでおり、IMFの支援が繰り返されているという歴史があります。この点で、ビジネスを安定させ日本円での利益を確保するための努力は欠かせません。パキスタンルピーの為替変動への備え、外貨準備不足に伴う部品の輸入規制が起こりえること等を念頭に、サプライチェーンを構築することをおすすめします。
課題やリスクはもちろんあるものの、競争が少なく、巨大市場であるパキスタンは日本企業にとって魅力的な市場と言えるでしょう。特に、先述した省エネ技術はもちろん、世界的に拡大傾向にある再生可能エネルギーに関連した技術・サービスは同国で需要が右肩上がりになることはほぼ確定しています。制度設計の段階から日本が関与している今こそ、環境技術を通じた国際展開の好機です。環境インフラの次なる展開地として、パキスタン市場の可能性を検討してください。
 |
|---|
本政府/JICAの支援で首都中心部に設置された |
 |
|---|
北西部の仏教遺跡タキシラでは |
|
執筆者紹介 株式会社海外安全管理本部 プロフィール |
|---|
マクロ情報:パキスタン(2024年)
| GDP(百万米ドル) | 373,078 |
|---|---|
| 人口(百万人) | 236 |
| 1人あたりGDP | 1,581 |
- 本資料はJPRSIが信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性・確実性を保証するものではありません。
- 本資料に従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するもので、JPRSIは何らの責任を負うものではありません。
- 本資料へのリンクは自由です。それ以外の方法で本資料の一部または全部を引用する場合は、出典として「JPRSI(環境インフラ海外展開プラットフォーム)ウェブサイト」と明示してください。
ⅰ https://sekai-hub.com/statistics/un-pakistan-population-pyramid#google_vignette
ⅱ 冒頭写真:首都イスラマバードのランドマークでもあるファイサルモスクは、アジア最大級
ⅲ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1972/s47-shiryou-6-5.htm
ⅳ https://number.bunshun.jp/articles/-/855365
ⅴ 出所:三菱UFJ リサーチ&コンサルティング
https://www.murc.jp/library/economyresearch/analysis/research/report_240930/
ⅵ https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?locations=PK
ⅷ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/oda/oda_keitai.html