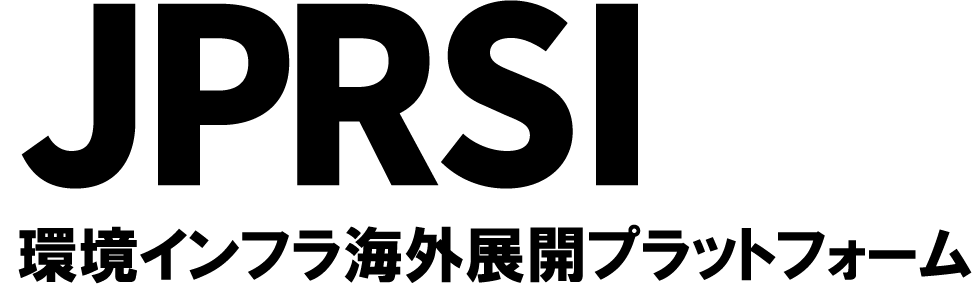活動記事:セミナーレポート
2024年度 第5回JPRSIセミナー
「環境に関する主要国際会議報告」

| イベント名 | 2024年度 第5回JPRSIセミナー「環境に関する主要国際会議報告」 |
|---|---|
| 開催日 | 2025年2月7日 16時~19時 |
| 開催方法 | 東京都内にて対面開催 |
| 概要 | 2024年後半に開催された、重要で注目度の高い気候変動COP29、生物多様性COP16、INC5の各国際会議について、環境省担当官より成果や今後の動向を報告し、国内外の政策・ビジネスに与える影響について講評しました。 またインドネシア大使館環境アタッシェより(リモート参加)、現地における環境法規制や現地の動向、開発ニーズについても紹介しました。 セミナー終了後には名刺交換&交流会を実施し、環境省担当官や参加者のネットワーキングが促進されました。 セミナー登壇者情報については、下記「関連資料」ページをご覧ください。 |
| 関連資料 | https://jprsi.go.jp/ja/static/activity-archive/2024/r6_seminar5_report |
イベントの様子ⅰ
 |
|---|
熱心に質問する参加者 |
 |
|---|
オンライン登壇中のインドネシア大使館員 |
主要国際会議の成果と国内外ビジネスや政策に与える影響
環境省地球環境局長の挨拶に引き続き、『国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)』、『生物多様性条約第16回締約国会議(CBD-COP16)』、『プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会(INC-5)』の結果が紹介され、参加者との間で時間を超過して活発な議論が行われました。
『国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)』報告
①主要テーマの1つが気候資金で、2035年までに少なくとも年間3,000億米ドルを途上国支援の目標として決定し、気候変動対策の実施に必要な資金支援についてCOP30(ブラジル)で議論される予定であるとの説明がありました。また、日本のNDC(国が決定する貢献)としては、2050年のネットゼロに向けて、2013年度比で2035年度に60%、2040年度に73%を削減して行くという目標を政府案として作成していることが紹介されました。
②GHG排出量の削減吸収量をITMOs(協力的アプローチの実施により国際的に移転される緩和成果)にするために必要な承認のプロセスや項目様式が決定されたことが紹介されました。今後のJCM(二国間クレジット制度)においてはプロジェクト開発の拡大が重要であり、環境省としては、民間JCMで出てくるクレジットを承認しITMOsにできるようにソーシング活動を官民一体で進めて行きたいこと、また、それを支える指定法人の立上げを進めて行くことの説明がありました。
③36件のセミナーと11社の技術展示を通して日本の環境技術を紹介したジャパン・パビリオンは国際的にも珍しく毎日盛況で高い評価を得たこと、各国の大臣や大統領など多くのVIP来訪者にもアピールできたことが報告されました。他方、COP30では、ジャパン・パビリオンの規模を縮小せざるを得ない可能性があるため、今後の状況についてはタイムリーに情報発信していく予定であるとの説明がありました。
『生物多様性条約第16回締約国会議(CBD-COP16)』報告
生物多様性条約の目的は生物多様性の保全、持続可能な利用、そして利益配分です。COP16にはビジネス・NGO・メディアなど多様なステークホルダーが参加し、過去最大規模の参加人数となりました。COP16の成果として、途上国が持つ豊かな生物多様性から得られる利益が衡平に配分されるようにするために、DSI(遺伝資源のデジタル配列情報)の使用により得られる利益の配分に関するメカニズムを確立できたことが紹介されました。また、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」というネイチャーポジティブの実現を図るため、生物多様性のビジネスへの組込み(主流化)が重視されており、企業がまず自社の生物多様性への影響を把握・評価・開示することに取り組むことがますます求められているとの説明がありました。
『プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会(INC-5)』報告
2022年のUNEP(国連環境計画)総会で「プラスチック汚染を終わらせる条約」の策定が合意され、交渉が始まったが、各国の立場の違いが大きく、今回も合意には至らなかったことが紹介されました。一部の企業・企業連合は公平な競争のためにも「国際的なルールが必要」と主張しており、WHO(世界保健機関)等はマイクロプラスチックや添加・吸着化学物質の健康影響に注目しています。プラスチックの生産(上流)における対策を重視する国(EU、高野心グループ)と、廃棄物管理(下流)対策のみでよいとする国(産油国)が対立している中で日本は中間的な立場であること、日本は廃棄物管理に関して技術的な強みがあり、条約交渉の進捗にかかわらず国際協力を続けていく必要があると考えていることの説明がありました。
インドネシア新政権と環境・気候変動協力の展望
在インドネシア日本大使館一等書記官がオンラインで登壇し、2023年10月に大統領が10年ぶりに交代し、2045年までの先進国入りを目標に掲げて貧困の撲滅・格差是正や8%の経済成長を目指している現地の様子が紹介されました。新政権は2060年までのネットゼロ達成を目指し、カーボン・プライシングや炭素市場の活用にも積極的で、クレジットの国際取引も開始されました。JCMに関し、2024年10月にインドネシアの温室効果ガス排出削減認証制度とJCMの相互承認取決めを結んだほか、同年12月にJCM実施ルールを改訂しており、JCMのさらなる展開の可能性が見込めるとの説明がありました。参加者からはインドネシアにおけるJCMなどのプロジェクト展開の可能性や、森林・植林に関する動向など、多くの質問が寄せられました。
交流会
セミナー後の交流会は、参加者が環境省担当官と直接意見交換する人の列が目につき、また参加企業・団体どうしでも、COP29に開催地出展またはバーチャル出展した成果の共有について笑顔で話し合う姿が多く見えたのも印象的でした。予定していた時刻を超過して残ったかたも多く、率直な意見交換ができる良い機会となりました。
なお、会場にはタッチパネル式のモニターを設置し、新しいJPRSIウェブサイトやバーチャル展示を通じた自社技術アピールの可能性についてご確認いただきました。
 |
|---|
タッチパネル前で環境省担当官と意見交換 |
 |
|---|
参加者同士の会話も弾んだ |
ⅰ JPRSIでは環境インフラの海外展開に役立つ情報をお届けするセミナーを時開催しています。
会員登録(企業・団体登録/個人登録)をしていただくと、セミナーの予定がタイムリーに届きます。会員登録をされていない方は、ぜひご登録ください。
(企業・団体会員)https://jprsi.go.jp/ja/static/registration
(個人会員)https://jprsi.go.jp/ja/individual_member