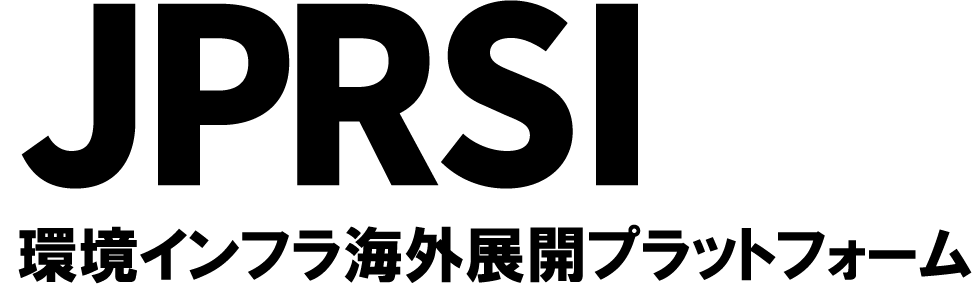活動記事:セミナーレポート
2025年度 第1回JPRSIセミナー
「JCMの最新動向」

| イベント名 | 2025年度 第1回JPRSIセミナー「JCMの最新動向」 |
|---|---|
| 開催日 | 2025年5月30日 10時~12時半 |
| 開催方法 | オンライン |
| 概要 | 二国間クレジット制度(JCM)は、2040年度までの累積2億トン程度の国際的な排出削減・吸収量の確保を目指して、更なるプロジェクトの形成促進が求められています。本セミナーでは、JCMに関する現在の状況、今後の展開方策、各国政府や関係機関との調整状況等、制度を取り巻く最新動向を環境省から紹介すると共に、UNIDO及びADBそれぞれの担当者より当該国際機関と連携したJCMプロジェクトの案件形成促進について発表いただきました。 セミナー登壇者情報については、下記「関連資料」ページをご覧ください。 |
| 関連資料 | https://jprsi.go.jp/ja/static/activity-archive/2025/r7_seminar1_report |
イベントの様子ⅰ
 |
|---|
UNIDOからJCM公募について案内 |
 |
|---|
集まった多くの質問に対応中 |
JCMをとりまく最新動向の報告・共有
まず、環境省担当官及び関係機関よりJCMに関する最新動向の情報共有・報告がなされ、続いて国際機関と連携したJCMプロジェクトの案件形成促進について、環境省担当官、国際連合工業開発機関(UNIDO)及びアジア開発銀行(ADB)の各担当者より説明がありました。事前に受け付けた質問のみならず、セミナー中も参加者より多くの質問が寄せられ、活発な質疑応答が行われました。
JCMに関する最新動向
5月28日にタンザニアとの署名が交わされてJCMのパートナー国が計30カ国となり、環境省は今後も引き続き署名国拡大に取り組んでいく方針であることが説明されました。なお、環境省による支援メニューである設備補助事業は引き続き継続していくものの、民間資金によるJCM拡大加速が重視されており、事業者の皆さまに、民間JCMの活用を前向きに検討いただきたいという期待が述べられました。
技術分野については、既存事例の多い再エネ・省エネ分野だけでなく、森林分野、廃棄物分野、そして農業分野等、多岐にわたる分野への拡大を期待する旨も説明されました。また、クレジット配分に関するパートナー国との交渉においては、当該国におけるJCMプロジェクトによって生じるBaU(Business as Usual)排出量とプロジェクト排出量の差分が、プロジェクト全体のGHG削減・吸収量として両国のNDC達成に貢献される点を、パートナー国に十分に理解してもらうことが重要であると説明がされました。
質疑応答では、民間JCMの具体的案件やアジア各国における二国間クレジット制度の進捗、新規パートナー国加盟に向けた動向について等の質問が寄せられました。民間JCMとして成立した案件を教えてほしいという質問に対しては、登壇者から、カンボジアにおけるREDD+の案件ⅱ、及びセネガルにおけるクックストーブの案件ⅲについて紹介がされました。
日本政府指定JCM実施機構(JCMA)ⅳの役割について
改正地球温暖化対策推進法に基づき、JCMのプロジェクト登録からクレジット発行までの制度運営・パートナー国との調整等の事務を担う日本政府指定実施機関としてJCMAが発足したことが紹介されました。JCMAでは、JCM案件形成からクレジット活用までの一貫したサポートとして、制度運営や各種手続きの遂行、クレジット発行におけるJCM登録簿の運営、及びJCMに関する情報発信ウェブサイト管理のほか、案件組成のための個別相談対応ⅴや広報活動等も行うことが説明されました。
国際機関と連携したJCMについて
各国際機関の地域性の強みを活かしてJCMプロジェクトの案件組成促進を行うこと等を狙いとして、ADBやUNIDO、欧州復興開発銀行(EBRD)といった国際機関と連携を行っていることが紹介されました。
ADBのJCMプロジェクト基金(JFJCM)は、アジア諸国を対象にADB内のローン(融資)、グラント(助成金)等の資金と組み合わせて活用できる点、また設備導入後のプロセスを含めてADBがサポートを行う点が特徴であることが説明されました。
UNIDOの公募に基づくJCMプロジェクト形成支援プロジェクト(UNIDO-JCM)は、JCMプロジェクトの数が他の地域として比較して相対的に少ないアフリカのJCMパートナー国における早期案件形成を目的として、UNIDOがアフリカ地域におけるネットワーク等の強みを持っている点、また、再エネ・省エネ等の脱炭素技術を導入するJCMプロジェクトだけでなく、廃棄物処分場におけるメタン排出削減に有効な「福岡方式」を用いたJCMプロジェクトも支援対象としている点等の説明がありました。
また、JCMパートナー国が増えつつある中央アジア・コーカサス地域におけるJCMプロジェクトの案件形成に向けて、当該地域に強みを持つEBRDとの連携開始を予定しており、今後数カ月~来年にかけて基金の立上げを図っていく旨が説明されました。
UNIDO-JCM:アフリカJCMパートナー国における再エネ・省エネプロジェクト及び廃棄物処理場における福岡方式導入プロジェクトの公募について
UNIDO-JCMに基づく、日本企業を対象としたアフリカJCMパートナー国でのJCMプロジェクト提案の公募(CfP: Call for Proposals)が、5月30日から8月29日までの間に行われているⅵことが紹介されました。また、提案の審査手続として、UNIDO内による事前審査及び技術・資金面での評価が行われた後、JCMルールに基づき、環境省を通じて当該アフリカJCMパートナー国とのJCM合同委員会にプロジェクト概要書(PIN:Project Idea Note)の提出が行われ、当該PINへの当該合同委員会によるNo objectionが得られた提案が採択される流れである旨が説明されました。
なお、UNIDO-JCMへの公募提案にあたっては、UNIDO Procurementポータルⅶが活用されること、提案を予定している日本企業による事前登録、公募資料の配布、質問・回答、そして申請書類の提出、提出等が行われること、及び当該ポータルの使用方法についての説明がありました。
アジア開発銀行・JFJCMの活用について
JFJCM基金の支援対象となるのは、ADBから資金支援を受けるプロジェクトであり、かつ低炭素技術導入のコンポーネントがあることが前提となること、またソブリン(公共セクターに対するファイナンス)及びノンソブリン(民間事業者の実施する案件)のいずれにも活用が可能である旨の説明がありました。なお、JFJCM基金は、エネルギー起源CO2削減の案件だけでなく、メタンやHFC等その他GHGの削減に資する案件においても活用が可能であることが紹介されました。参画にあたっては、各アクター(EPC/O&Mコントラクター、コンサルタント、事業者、投資家等)にとって、それぞれソブリン案件における国際競争入札機会(入札前のADBやホスト国へのコンタクト含む)や、FS業務や調達支援業務、施工管理業務等の受注機会等があることが説明されました。
ⅰ JPRSIでは環境インフラの海外展開に役立つ情報をお届けするセミナーを随時開催しています。
会員登録(企業・団体登録/個人登録)をしていただくと、セミナーの予定がタイムリーに届きます。会員登録をされていない方は、ぜひご登録ください。
(企業・団体会員)https://jprsi.go.jp/ja/static/registration
(個人会員)https://jprsi.go.jp/ja/individual_member
ⅱ カンボジアにおける民間JCM案件(REDD+):https://www.jcm.go.jp/kh-jp/projects/registers
ⅲ セネガルにおける民間JCM案件(クックストーブ):https://www.jcm.go.jp/sn-jp/information/513
ⅳ 日本政府指定JCM実施機構(JCM Implementation Agency: JCMA)
https://gec.jp/jcm/agency/index-ja.html
ⅴ 案件相談窓口は、
設備補助事業:jcma-contact@gec.jp
民間JCM:jcma-registry@gec.jp
ⅵ 「国際連合工業開発機関(UNIDO)による二国間クレジット制度(JCM)に基づくアフリカJCMパートナー国を対象とした脱炭素プロジェクト提案の公募について」
https://www.env.go.jp/press/press_04950.html
ⅶ UNIDO Procurement Portal
https://procurement.unido.org/